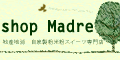最新情報は、ショップマドレFacebookページで随時更新中。
Facebookアカウント持っていなくても見られます(そのはず)◎
2017年04月18日
てらすくらす〜経済学のめがねで現代を見る〜 第一回「そもそも経済学って何?」のきろく。
ずいぶん日が伸びましたね。







日が伸びると、サマータイム、サマータイム、て思ってしまいます。
サマータイム、時計を1時間早めるから、自動的に早起きすることになるから、
そして早寝することにもなるから、いいと思うねんけどな、何かと。
まぁ生活の全てがまるのまま1時間変わるから、それが果たしてどうなんかわからんけど。
でも、国で例えば政策として決めたら、ある日から、”せーの”で時間変えられるって、なんか不思議だよな。
そして、ある日また、戻すのだよ。時間の概念がいろいろ変わるよな。
みんなで、せーので1時間、今までと違う時間軸を生きるねんで。すごくない?
はい、意味のわからない前置きが長くなりました。
先日、このブログでもちらっと紹介した、
途中、頭パンクして煙出たけど、おもしろかったので、
せっかくやしレポート書いておこうと思います

むっちゃざっくり印象的やったポイントを、自分なりの解釈とともにお伝えできたらと思います。
てらすくらす、第一弾は、滋賀大経済学部の中野桂先生による
Class01 “経済学のめがねで現代をみる”。
(このタイトルに惹かれて、参加申し込みを即決したと言っても過言ではない。経済学のめがねやで、めがね!
いろんなめがねを持っていると、たぶんいろんな見方ができて、きっとそれはとても面白い。世界が広がる。
経済学、も、自給自足的な暮らしをしても、やっぱりお金とは関わり続けるので、たぶんこのめがね持ってると、何かと便利で強くなれるはずなのさ!)
で、一回目。
テーマは、”そもそも経済学ってなに?”

おそらくいろんな業種の、年齢層もバラバラな参加者が集っている気がする。それも面白いポイント。高校生もいる。
今回含めて6回。みなさまどうぞよろしくお願いします。
経済。
たぶん、割とたくさんの人が、経済はお金のことやと思う気がする。少なくとも私はそう思っていた。
世の中の、お金の動き・流れ、それが経済

が、どうやらそれはちがうらしい。
ちがう、というか、それも経済の一つであるけど、”経済”というものの、ほんの一部分にしか過ぎない。
じゃぁ、そもそも一体経済って何やねん、というと、
”経世済民”= 世を経(おさ)め、民の苦しみを済(すく)う
を略したのが、経済のほんまの意味なんやってさ



お金、関係ない。
どちらかというと、仕組み?概念?
人が(”喧嘩をしたとしても”だと個人的には思う)にこにこ暮らせるようにするためにはどうしたらいいのか、
を問うものなのかな、経済学?
餓えないように。とにかく、みんながより良い暮らしをするためには、がテーマ、それが経済。イェー。
経済、英語で言うとEconomyなのだけど、こちらの語源も面白い。
Ecoはギリシャ語ではOikos(住処)、Nomos(法・制度)を表していて、
住んでるところにどんな”法”を作るか、ということらしい。
ちなみに、Ecology(生態・環境)は、Oikos(住処)+Logos(論理、理由)を表し、
住んでるところはどんな仕組みになっているのか、ということ。
住んでるところの仕組み(もうすでにあるもの)を知った上で、
より住みやすい環境を、自分たちの手で法や制度を制定することによって、整える、という感じ?
だから本当は、環境と経済はものすごく密接な関係にあるのさ。
お金の匂い、しないよね。

最近話題の、教育勅語。
ではなく、共育智欲語。すてき。
ちょっと今回真面目に聞きすぎたかな。1回目だしな、緊張する、仕方ない。
じゃぁなんで、今は経済と言ったらお金って思うのか。
経済にはいろんな種類がある。
あるねんけど、いっぱいいろんな名前でてきた気がするけど、忘れた。
とりあえず大きく分けると、以下2つ。
市場経済と、非市場経済。
定義の説明は、んー、できないけれど、市場経済は経済の中でもほんのほんのほんの一部。
そして、これが世に言う”経済”。
それ以外は全部非市場経済。
家の中で、お母さんがご飯を作ったからって言って、お金を払ったりはしない。
(互助の経済というらしい)
空気。吸ってるし吐いてるけど、お金払わへん。
所有権のないもの、国有地とか公共財とか。お金が直接関わらんかったら非市場経済なのか?
税金とか絡んだらどうなるんやっけ?忘れました。
まぁ、それはいいとして。
この、ほんの一部にしか過ぎない、市場経済によって、我々は右往左往しているということになる。影響力大。
とりあえず、”チビだけど侮れない”のが、市場経済らしいよ、チェケラ。
だからこそ、の、経済学なのだ。
”経済学を研究する目的は・・・・・
どうすれば経済学者によって
欺かれないで済むかを学ぶことにある ”
byジョーン・ロビンソン

先述の通り、エコシステムありきのエコノミーであるのが本来の姿(つまり、住んでいるところの仕組みを知った上で、より住みやすい環境を整えるために、新たな仕組みや制度を自分たちで加える、という順番)のはずなのに、今は、明らかに、そのバランスが無視されている、の図。
消費がでかすぎて、生産に無理が生じたり、廃棄に無理が生じたり。(エコシステムに適っていない。)
今、この世に存在している物質は全てもともとは土からできている。全て。
プラスチックを例にとると、プラスチックの消費はつまり石油の消費であり、石油ももともとは土が時間をかけて出来上がった形なのだけど、それが使うペースが早すぎて、土から石油になるペースが追いついていない。
さらに、捨てた後も、プラスチックは土に戻るのにあまりにも時間がかかる。そんな感じ。
ちなみに、最近ではこんなプラスチックも開発されている。すてきなやつ。材料はキャッサバ。
それが経済イェー。
はい。
ついつい、どんな話を聞いていても、やっぱり自分ごとで聞いた方が興味が湧くので、
自分の仕事(マドレね)とつなげて聞いていて、いろいろハッとする点もありました。
経済における、陰と陽の話。
食でいうと、マクロビの考え方の主軸となっているのも陰と陽。
なので、これも共通していてとても面白かった。
陽は、ギュッと塊みたいなイメージで、エネルギーがギュギュギュっとなっている感じ。
熱い鉄の塊みたいな。
(マクロビ的に言うと、肉・塩は陽が強くて、野菜ではごぼうとか人参とかが陽。調理法ではオーブンで焼くのがかなり陽で、火を使うことそのものが陽。)
陰は、ぐんぐん伸びたり広がったり、拡散のイメージで、冷えていくような。分裂。
(マクロビ的には、砂糖・アルコールがかなり陰、果物も陰、野草は割と陰、みたいな。陰のものを食べる時は、陽の調理法で食べようぜ的な。(果物やったら干したりとかね。))
経済でも同じで、陽は、中央集権的、中野先生曰く、「アメリカ軍型」。
(でっかい会社の、その下の会社の、系列の、なんとかかんとか。大企業とか基本的な経済システムはこっちかなぁ?)
陰は、分権的で、「アルカイダ・ゲリラ型」。
(もしやもしや、ホホホ座(京都にある面白い本屋さん。元「ガケ書房」)はこれにあたるのかな?
前行った時、ホホホ座の2階の店主さんと喋った時に、誰でもホホホ座になってもよくて、何をやってもいいのだ、と言ってはってそれがむっちゃおもろいと思ったのだ。)
陽は、強いし、システム的におそらく管理・コントロールしやすいのだけど、
その代わり、一つどこかが崩れると、ドミノ式に全部ダメになっちゃう。
陰は、みんな自由だから組織としては弱いのだけど、自由さが持つ耐久性というか、
どんどん新しいリーダーも出てくるし、まぁみんなリーダーみたいなもんだから、へこたれない。
たぶん、そんな感じ?
(ただ一点だけ、陽にグローバル、陰にローカルが入っているのだけど、マクロビ的観点からいくと、逆な感じはするんだよな。
まぁ、そもそも、マニアックな話だけど、マクロビの陰陽論は、もともとの中国の陰陽論と逆らしいから、まぁ、なんとも言えない。)
こういう話を聞きながら、マドレはどっちだろう?となるわけさ。
ちょっと最近、働き方の実験をしていて、ちょっと陽寄りになってるのかな、となりながら聞いていたのさ。
もともと、マドレは陰よりだったような気はする。まだまだ実験中。
だけど、やっぱり陽が強くなりすぎる(と感じる時があるのだ、たまに)と、うまくいかないのだ、どうやら。
むっちゃ関係ないのやけど、今回の講義の中で、行動経済学の話があって、その中のオススメの本(「実践行動経済学」)の原題が、"Nudge"やって、
もう、Nudgeと聞いた瞬間から、頭の中に浮かんだ、Monty Pythonのこのネタ(イラっとするから嫌いなんやけど。)。
でも、Nudge Nudge,連発で、たぶん、私がNudgeて言う単語を覚えたのはこのネタがきっかけなのだな。
ツンツン。つつくこと。動画リンク貼っとくけど、たぶんみたらイラっとするから、オススメはしない。笑
世の中をつつきたいよな。たぶん何度かブログでも書いてきたけど。マドレの裏テーマ。
はい、あんまりまとまっていないけれど、このままパラパラのまんまいくよ。
そして、面白かった、おそらくこれからずっと鍵になってくるのが、”社会的余剰”のお話さ。
社会的余剰。
その説明をするのに必要な2つのキーワードが、”消費者余剰”と、”生産者余剰”。
この2つを合わせたものが、社会的余剰、たぶん。
まず、消費者余剰。
例えば、おいしそうなおやつがあったとする。
値段書いてない。たぶんまだ、準備中。
”ん〜おいしそうだなぁ、食べたい。。。いくらくらいやろう?
300円くらいかな。”
と思っていたら、
なんと、200円だった!
となった時、100円得した気持ちになる。
これが、消費者余剰。

久々に金沢に一人旅行った時に泊まったゲストハウス白さん。
たぶん、今まで行ったゲストハウスの中で一番居心地が良かった。
スタッフの人たちもみんな本当に親切で、ほんまになんというか、
この仕事、好きなんやろうなぁというのを感じて、それだけでもう幸せな気持ちになる。
素敵スポットもたくさん教えてもらって、いい旅になりました。
お金でいうと、ドミトリーで泊まったので、1泊3500円+夜ご飯食べに行くためにチャリを借りて計3800円。
だけど、本当に、いくら分得したかとかお金では換算出来ない、言葉では言い表せない、この”幸せ感”。
いくら分得した、という感覚はないけれど、たぶん経済のめがねで見ると、消費者余剰が本当に大きい滞在。
そして、生産者余剰。こちらは、消費者余剰の逆ね。
”むっちゃ頑張って作ったけど、んーでも売れるかなぁ自信ないなぁドキドキ・・・
いくらくらいにしよう、、、、手間もかかってるし、せめて150円で売りたいところやけど、
一般的には100円くらいで売られてるしなぁ。。。
100円にしとかなあかんかなぁ。。。”
と思っていたら、(100円では安すぎると言われたりしつつ)200円で売れた!
となった時、100円?50円?わからないけど、とても嬉しい気持ちになる。
これが、生産者余剰。
そして、この2つが同時に起こる時、生まれるのが、社会的余剰。
上のケースだと、
買う側は、300円出す気持ちの人と、売る側は、100円かな、と思っていたものが、
200円で買えて、売れた時、どちらもハッピーになる。
この、社会的余剰が増えた時、そこらじゅうでハッピーが増えるということにつながる、という仮定。
つまり、みんなハッピーになるためには、社会的余剰を増やしたらいい、ということ。
じゃぁ、どうしたらいいのか。
たぶん、生産者余剰を増やすために必要な事の1つが消費者教育。
社会全体での価値観の見直し。
消費者自身が、賢く、強くなること。自分で判断できるようになること。
判断するためには、もちろん直感も大事だけど、情報の取捨選択。
値段の安い高い以外の基準での、選ぶ軸を持つこと?
ある意味、自分の持つめがねを増やすということ。
消費者余剰を増やすための仕組みの一つが、適切な広報・デザイン。
正しい情報を、消費者が知ることによって、お得感が増す。
ただ、このデザインや広報も、お金・時間・手間はかかる部分でもあるので、
その分、結局値段は上がるのかもしれないけれど。
でも、デザインの威力はすごい。
身近なところでデザインの威力を感じたいい例は、”菜ばかり”(愛東産圧搾絞り菜種油)。
菜ばかりが、菜ばかりになる前、”菜の花油”だった時代からマドレでは愛用してきて、販売もしてきたけれど、
菜ばかりにリニューアルしてからの、売れ行きが、もう、本当にわかりやすく、変わったのを実感。
デザイン可愛くなって、ミニサイズも登場したから、お土産やギフトの定番にもなったし、
あげて嬉しい、もらって嬉しい、生産者も消費者も嬉しい仕組みになったと思われる。


金沢21世紀美術館の敷地内にある茶室の縁側と、なんやろ。笑
全体的に木で、”いい感じの建物やなぁ〜”と、勇気出して中入ってみたら、
おじさんが出てきて、いろいろ茶室について説明してくれた。
この茶室が、鎌倉にあったり料亭の隣にあったり、5回くらい移築されてきてこの場所にたどり着いたこと、
そして移築ができたのは、釘一本も使わない組み木で作られた伝統工法だからということ、
金沢では、大工さんたちが無料で伝統工法を学べる3年間のコースがあるということ、
そうやって金沢の伝統が守られ、さらには県外にも進出しているということ、
などを教えてもらいました。
これにより、茶室が、ただ眺めていたいい感じの建物から、”時代をまたいでいろんな土地を旅してきて大切にされてきた建物”に変身を遂げることとなる。
茶室に入るのは無料、だけど、これもある意味消費者余剰?
そしておそらく、おじさんは、いろんな人に金沢の素敵を知ってほしいから、それを興味深く聴いてもらえたことにより、生産者余剰を生み出していることになるのかな?
たぶん、生産者余剰を増やすのって、今の全体的に低価格なものが売れる時代では本当に、大変なことなのだと思うけど、
やっぱりこのことに関しては、つまるところ、
”好き”かどうかなんかな、というところにどうしてもたどり着く。
何度か私自身も正直言うとマドレ始めてから、折れかけたことある。
ついつい凝りすぎて、値段を上げたくなるけど、あげられないジレンマに陥ったり。
なんでこんなにも手間をかけたんだ、バカなんじゃないか、私は!的な。
とにかく、値段を決めるのは、何よりも難しい。野草とかもね。

金沢は、金沢城や兼六園を始め、そこら中に庭、そして土が残っていて、つまりは野草の宝庫。
ついつい、探しちゃうのだ。そして、見つけると、嬉しいのだ。
ミツバ、むっちゃ生えていたよ、の図。
これは確か、鈴木大拙館の散策コースで発見?
でも、こっちゃうのは、やっぱり好きだからだし。
(ヴィーガンも、有限性の中の無限性的な、クリエイティブ感が好きなのだ。 )
野草摘んでるのも、やっぱり好きだからだし。
(自給自足的な暮らし・・・というよりお金に頼らない暮らしに興味あるし、そこらに食べ物生えてるねんで!しかも美味しいねんで!と言いたい。世話していないのに、勝手に生えてきてくれるなんて、奇跡以外の何物でもない)
デザインについこっちゃうのも、やっぱり好きだからなのだと思う。
(全部独学でやってるから、自分の求めるクオリティと自分の技術の差異と効率性に悩んでいるけれど。これからも続けるべきかどうかで。)
たぶん、これがすべて、全く好きじゃないことやったり、
効率ばっかり追い求めてたりして、
苦しみの中で生み出して、販売していたら、
おそらく、続けられていないと思うし、”生産者余剰”は生まれることはないと思う。
たぶん、どれだけやっても満足しないのだと思う。
やってやってる感とか、しゃーなしに作ったり仕事してたりしてたら。
だから、やっぱり、好きなことをみんなやったら、それだけで自然と社会的余剰は増えて、
つまりは、幸せに、結局のところつながっていくんやろな、と思う。
好きなことやってたら、やっぱり多少のことでは諦めないし、
嫌なこともやるようになる、その好きなことを実現するために、それが避けては通れない道だとすれば。
そんなことが普通になる世の中になったら、ほんまにむっちゃおもろいやろな、と思うし、
なんとなく、碧いびわ湖は滋賀県でその輪を広げる仕組みの一端を担っているような気がして、
目が離せないでいるのだ。
世の中には、いろんな役割の人がいて、
作る人もいて、考える人もいて、食べる人も、面白がって見てるだけの人も、
人についついお節介をやいてしまう人も、なんとなく人を引っ張っていかないと気が済まない人も、
どうしても困っている人を見放せない人も、植物が大好きな人も、
動物が大好きな人も、人間が好きな人も、お金が好きな人も、仕組みが好きな人も、
分析が好きな人も、何かと何とかしたいと思っている人も、
とりあえず面白そうだから行って見る人も、ニコニコ座ってそこにいる人も、
たぶん、それでいい気がする。
みんな、たぶん、ほんまに好きなことをしたら、それで世の中は本当は成り立つはずなのだ。
と、最後はむっちゃ熱くふんわりまとめておきます。
唐突。
たぶん、経済もそういうもんで、というか、今書いたことを、経済のめがねから、
どう見て、どう分析、解釈、説明できるのか、果たしてできるのか、というのが、
これから残り5回(では足りないかもしれないけど)の目標だぜ。
てらすくらすの雰囲気、伝わりましたか?





最後の方は、かなり勢いで書いたけど、あえて修正せずにこのままいきます。
へんてこで、長い文章、読んでいただきありがとうございました

第2回目もまたレポート書くので、お楽しみに

やたら”ダサくないこと”にこだわる理由。
「私とマドレ①」長い長い長い長い長い長ーーーーーーい振り返り。
メディア掲載のお知らせと、ぶつぶつ(久々)。
VEGANおせち2017の記録<後編>。
VEGANおせち2017の記録<前編>。
メールアドレス変更しましたー&今週のマドレ。あんど鳥取旅の記録(もう1ヶ月も経つなんて!)。
「私とマドレ①」長い長い長い長い長い長ーーーーーーい振り返り。
メディア掲載のお知らせと、ぶつぶつ(久々)。
VEGANおせち2017の記録<後編>。
VEGANおせち2017の記録<前編>。
メールアドレス変更しましたー&今週のマドレ。あんど鳥取旅の記録(もう1ヶ月も経つなんて!)。
Posted by shop Madre at 22:54│Comments(0)
│ちょっとした記録。